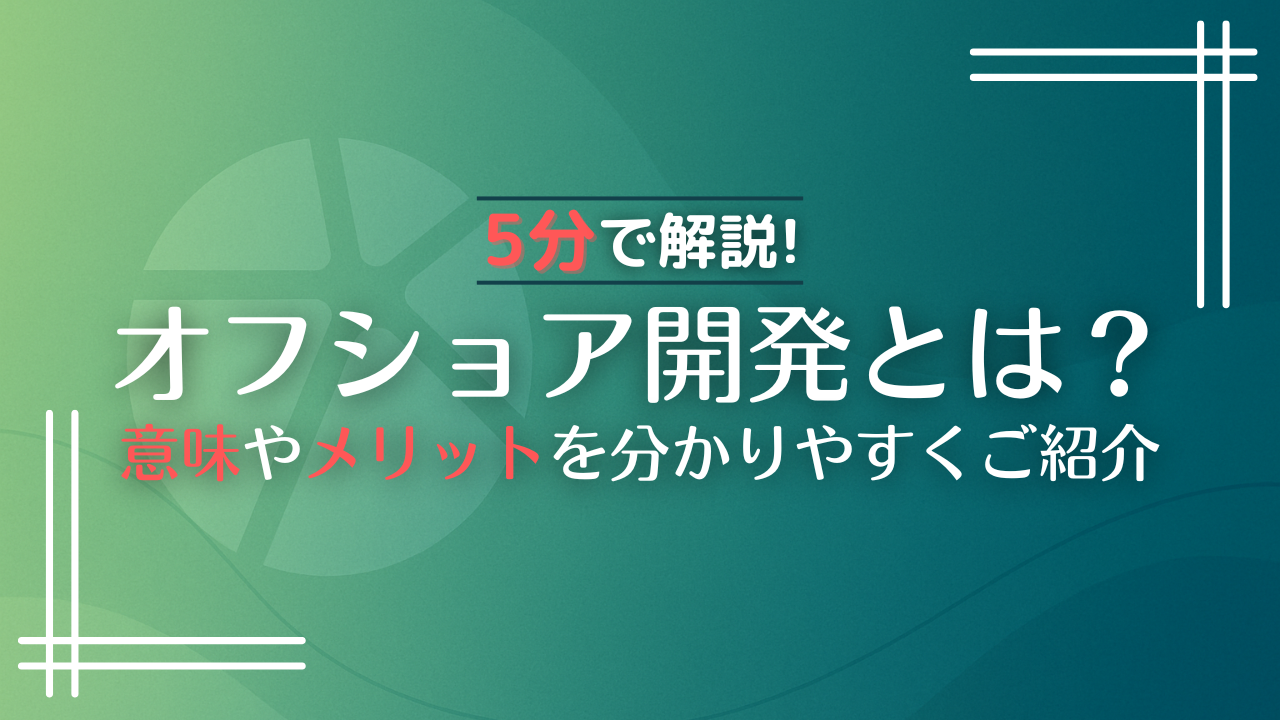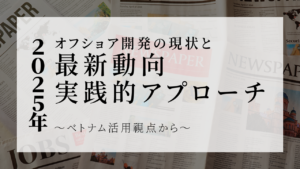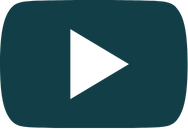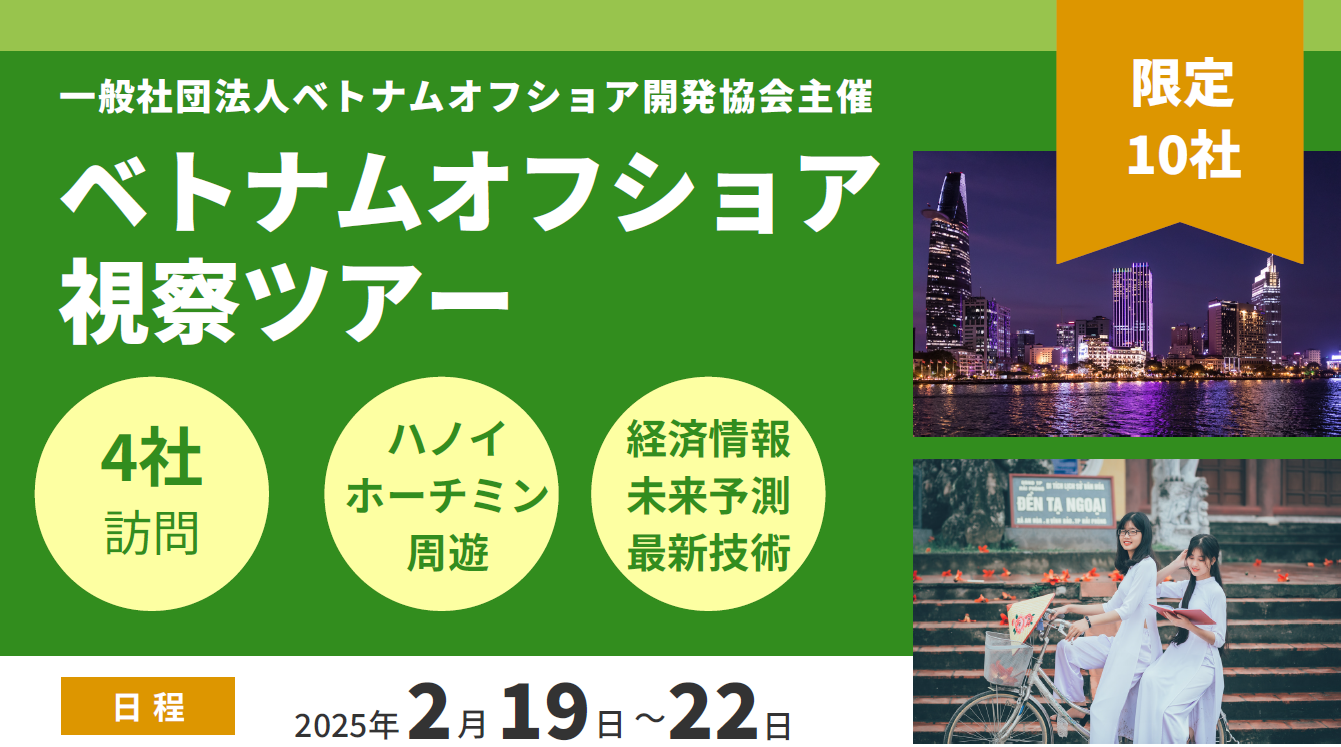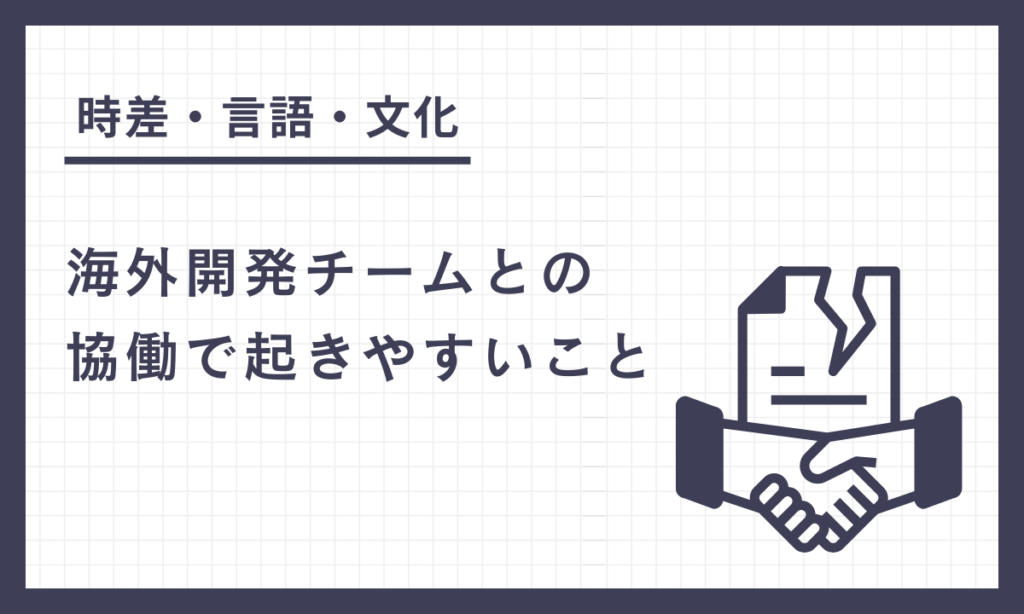
こんにちは!VOC事務局です。
「ちゃんと伝えたはずなのに、なぜかズレている」「たしかに確認したのに、認識が違っていた」
これは、海外の開発チームと仕事をしていると、誰もが一度は経験する感覚ではないでしょうか。
たとえば、日本側がSlackで送った質問がなかなか返ってこなかったり、週明けに確認したタスクが、思っていた形と違うものに仕上がっていたり。確認しても「これは言われてない」「その認識はなかった」と返ってくると、思わずイライラしてしまうこともあります。
このような“伝わったつもり”と“受け取ったつもり”のズレは、単に「説明が足りなかった」「スキル不足だった」という話では片付きません。背景には、時差・言語・文化という3つの大きな壁があり、私たちが普段あまり意識しない“前提の違い”が横たわっています。
海外のチームと良好な協働体制を築くためには、この見えづらい壁に気づき、丁寧に乗り越えていく必要があります。
この記事では、海外開発チームとの仕事で起きやすいズレの正体を紐解きながら、現場でできる具体的な工夫や考え方を共有していきます。
この記事はこんな人にオススメ!
1.時差の壁:夜に投げて朝に返る「非同期地獄」

海外チームとの協働において、最初に直面するのが時差の壁です。特にアジア圏(ベトナム、フィリピン、インドなど)では、日本との時差は1~3時間程度と小さく感じるかもしれませんが、実際の業務においては想像以上に大きな影響を及ぼします。
■ タイムラグがコミュニケーションを“非同期”にする
たとえば、夕方に日本側が確認のメッセージを送ると、相手がそれを読むのは翌日の朝になります。すると、返事が返ってくるのはさらにその数時間後。1つのやりとりに1営業日かかることも珍しくありません。
これにより、以下のような現象が起こりがちです。
- 仕様の確認に時間がかかり、タスクが進められない
- 回答が遅れることで、判断が先延ばしになる
- 伝えた内容に対してすぐに補足ができない(別の解釈で進んでしまう)
このような状態が続くと、プロジェクト全体のスピード感が失われ、両者にとってストレスが溜まる原因になります。
■ “質問したのに返事がない”は、届いていないだけかも?
もうひとつありがちなのが、「質問したけど返事がない」「資料を送ったのに何も反応がない」といった“無視されたように見える”状態です。
これも時差によって、ただまだ見ていない・確認できていないだけということが少なくありません。しかし、発信側は「読んでないの?」「無視された?」と感じてしまいがちです。
この認識のズレは、コミュニケーションの信頼関係にヒビを入れてしまうため、予防が必要です。
■ 時差を前提に「仕組み」でカバーする
こうした問題を防ぐためには、単に「早めに投げる」だけでは不十分です。
チーム全体で「時差がある前提でどう情報を回すか」を仕組みとして設計しておくことが重要です。
たとえば:
- 「夜に確認しておいてほしいことは、朝イチで対応する」などのルールを作る
- SlackやChatworkでは“未読スレッドの整理”を徹底する
- 毎朝15分の朝会を設定し、前日の確認・補足をする
- NotionやBacklogなど、非同期でも追えるタスク管理を導入する
また、「読んだらリアクションをつける」「確認したらスタンプ」といった、簡易なアクションをルール化するだけでも、誤解やイライラを防ぐ効果があります。
2.言語の壁:「話せる」≠「伝わっている」

海外チームとの協働でしばしば課題になるのが、言語の壁です。
多くのベトナム人エンジニアは日本語検定N3〜N2レベルのスキルを持ち、日本語での会話やチャットがある程度できる人も増えています。BrSE(ブリッジSE)を通じたコミュニケーションも一般化しており、「言葉が通じないから難しい」という時代ではなくなりました。
しかし実際には、“言葉が通じても、意図が伝わらない”という問題がしばしば起きます。
■ あいまいな日本語は“翻訳”で消える
たとえば、「そこは臨機応変でいいよ」「可能であれば〇〇してください」というような表現は、日本の開発現場ではよく使われます。しかし、これを翻訳するとどうなるでしょうか?
- “臨機応変” → どの範囲まで許されるのか?
- “可能であれば” → やらなくてもいいと判断される可能性
日本語では文脈や空気で補われるあいまいな表現も、翻訳を通すと意味が削ぎ落とされてしまうのです。しかも、それが設計書やタスク指示など“業務の根幹”で起きると、作業結果に大きなズレが生まれてしまいます。
■ 「報告」「相談」の頻度・中身が合わない
もうひとつの問題は、報連相の粒度です。
- 日本:「ちょっと気になったんですが…」という相談から入る
- ベトナム:実行してから報告 or 大きな問題になってから報告
これは「文化」でもあり、「言語習慣」でもあります。とくにBrSEが橋渡しをしている場合、エンジニア→BrSE→日本側と伝言ゲーム的に報告が伝わるため、ニュアンスの微妙な違いが生じやすくなります。
■ BrSEも万能ではない
BrSEは「日本語ができるだけでなく、ITの知識もある」貴重な人材です。ただし、彼らが全能なわけではありません。
- 工数や負荷によってはすべての会話に同席できない
- 日本語が堪能でも、プロジェクト固有の言葉や業務用語に弱い
- “翻訳”と“通訳”の違いを理解して使い分ける必要がある
たとえば「デグレ」「機能間連携」「疎通確認」などの日本特有の用語は、BrSE自身がその業務を体験していないと正確に伝えきれないこともあります。
3.文化の壁:責任・判断・報連相の感覚が違う

“言語が通じても、文化が違えば通じない”――
これは海外チームと仕事をするなかで、しばしば直面する現実です。
■ 「気づいていたけど、言わなかった」はなぜ起きる?
たとえば、こんな経験はないでしょうか?
「ここ、明らかに仕様と違うよね?」
「あ、そうですね。実は途中で気づいていたんですが…」
これは、「言えばよかったのに!」と思うところですが、ベトナム側からすると“余計なことかもと思って黙っていた”という意識であることも少なくありません。
日本では「気づいたら報告する」のが当然とされますが、海外では「自分の担当ではないことには触れない」という文化もあります。
■ 指示待ちと自主判断のギャップ
もうひとつよくあるギャップが、「どこまで指示しないと動けないのか」です。
日本人の感覚では、「これって、普通こうするよね?」と思うことも、ベトナム側では「それは指示されていないからやらない」という判断になることがあります。
- 「これやっておいて」は、“どの粒度まで”やればいいか?
- 「必要に応じて」は、“誰が判断するのか”?
こうした“あいまいな責任”の扱い方に対する認識が、日本とベトナムでは異なることが多いのです。
■ 「察する」は通用しない。言葉にする努力を
日本では、仕事の進め方において「空気を読む」「言わなくても分かるだろう」が強く根付いています。しかし、海外のメンバーにとっては、それはただの説明不足に映ります。
海外チームと協働する際は、「察してくれるだろう」ではなく、「自分から言語化して共有する」姿勢が求められます。
4.解決に向けた視点:「伝え方」「確認の仕方」「共有の仕組み」
ここまで見てきたように、海外開発チームとの“ズレ”は、時差・言語・文化といった目に見えにくい要素によって引き起こされます。これを完全にゼロにすることは難しいですが、「起きにくくする」「起きてもすぐに気づいて対応できる」仕組みづくりは可能です。
■ 情報共有は「話す」より「残す」
ズレを防ぐ最大のポイントは、会話ベースの共有から“記録ベース”の共有へ移行することです。
- 口頭やチャットだけで済ませず、要点はドキュメントに残す
- 要件・仕様はNotionやConfluenceに明文化する
- 対応履歴やQAはBacklogやRedmineなどで一元管理する
こうした「見える化」によって、認識の確認とすり合わせが“仕組み化”されるため、個人の記憶や言葉に頼る必要がなくなります。
■ “伝える”ではなく“共有する”を意識する
日本の現場では、「伝えたから終わり」「言ったんだから分かってるはず」という前提になりがちです。
しかし、海外との協働では「相手がどう受け取ったか」にまで目を向けなければ、すれ違いはなくなりません。
たとえば:
- 設計書や仕様に「この意図でこうした」とコメントを加える
- 仕様説明のあとは「再説明してもらう」ことで理解度を確認する
- 文化的に理解されにくい概念は、具体例とセットで共有する
こうした工夫を“面倒”と感じるかもしれませんが、1回のすれ違いが生む損失を考えれば、事前共有の方がはるかに効率的です。
■ BrSE・PMだけに頼らない“協働体制”を
「BrSEが優秀だから大丈夫」「PMが確認してくれるはず」と属人的な期待に頼ると、ボトルネックやトラブルの火種になります。
理想は、「誰がどこでズレに気づいても対応できる」状態を目指すことです。そのために:
- ドキュメント・チェックリスト・エビデンスを使って属人化を防ぐ
- 毎週の定例で「お互いに違和感があるところ」を出し合う文化を作る
- 教える・教わるの関係を超えて、“共に考える”関係性を築く
ズレのない協働は、“1人の頑張り”ではなく、“チームの習慣”によって実現されます。
まとめ:海外チームとは、“伝える”より“共有する”を設計する
いかがでしたか?
海外チームとの協働には、どうしても“ズレ”がつきものです。
ただし、それは「相手が悪い」でも「自分の伝え方が下手」でもなく、前提が異なるからこそ自然に生まれるものでもあります。
そのズレを見ないふりをするのではなく、前提にしたうえで仕組み・ルール・習慣で補うことが、健全な協働の第一歩です。
ときには、すれ違いにイライラしたり、不安になったりすることもあるかもしれません。でも、だからこそ「ちゃんと伝わる」喜びや、「一緒に前に進んでいる」という実感が生まれるのもまた、海外協働の醍醐味です。
1月23日|リアル開催|「AI時代のオフショア戦略」セミナー受付中
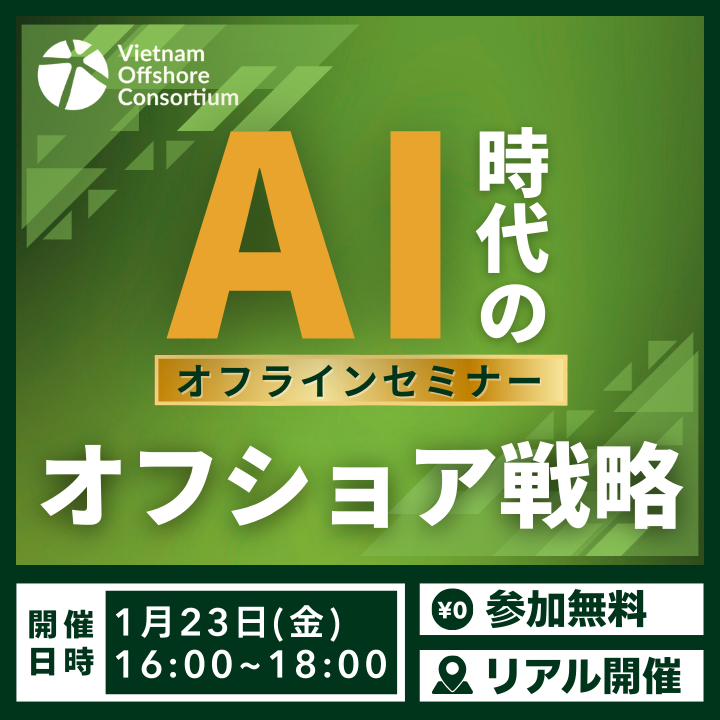
生成AI、ローカルLLM、AI駆動開発…。
急速に進むAI技術の中で、「オフショア開発の役割はどう変わるのか?」
そんな疑問を持つ企業が増えています。
今回のリアルイベントでは、AI×オフショアを実務で扱う4社が集まり、最新事例と、現場で起きている“リアルな変化”を共有します。
AI活用とオフショアの“これから”を知りたい方に向けた濃い内容となっていますので、情シス・システム部門の責任者の方、開発マネージャーの方、外注選定を担う担当者の方は、ぜひ詳細をご確認ください。
メール配信申込みのご案内
ベトナムオフショア開発協会では、
日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。
本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。
セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。