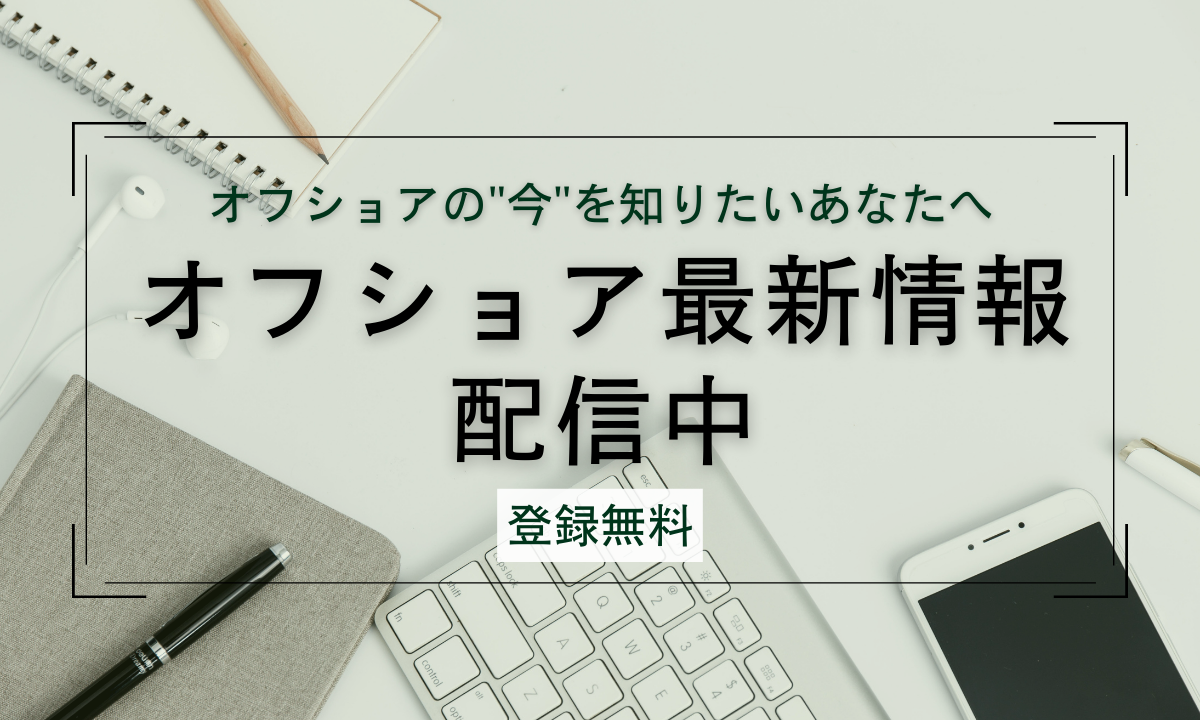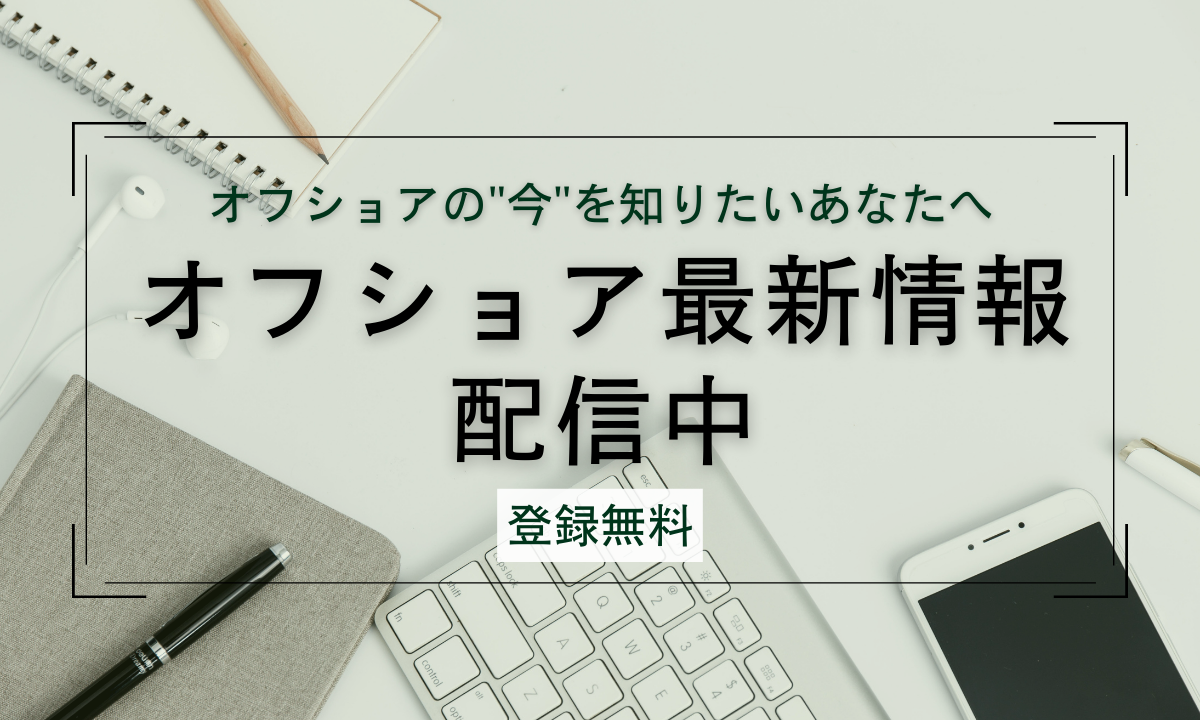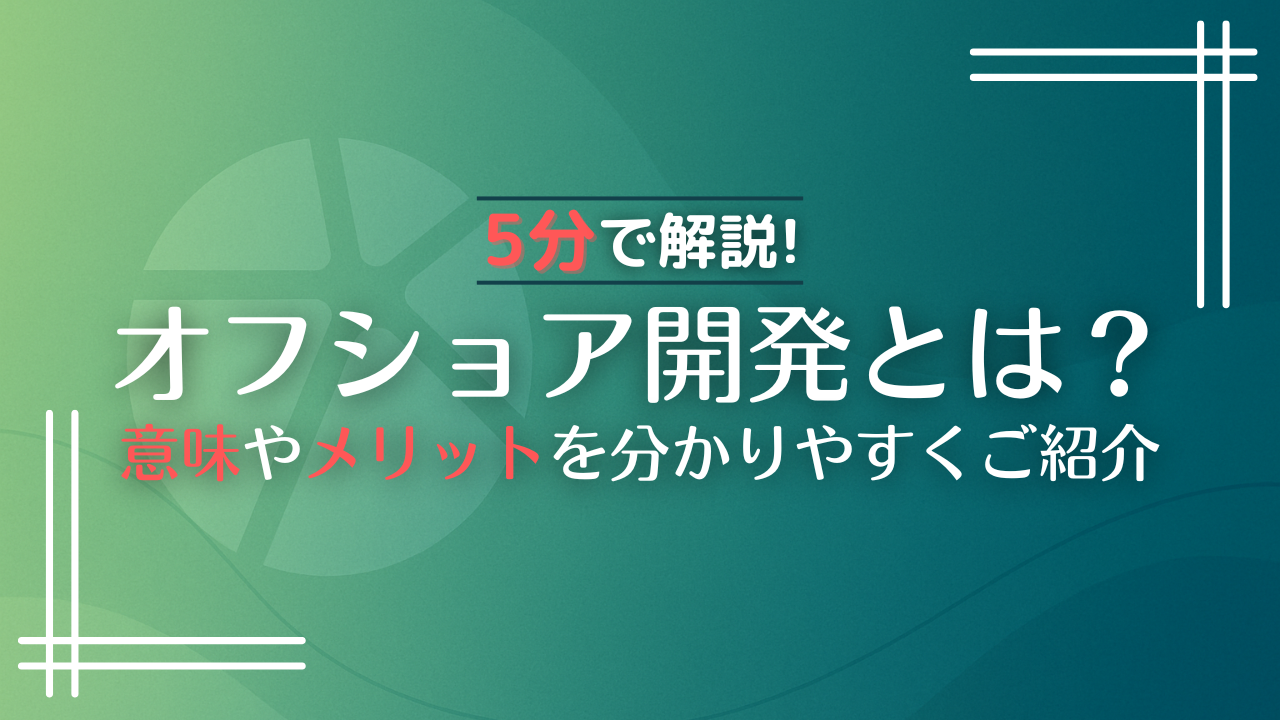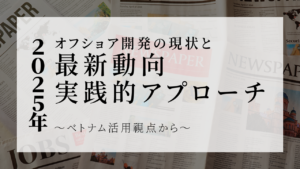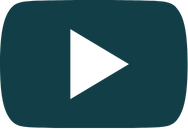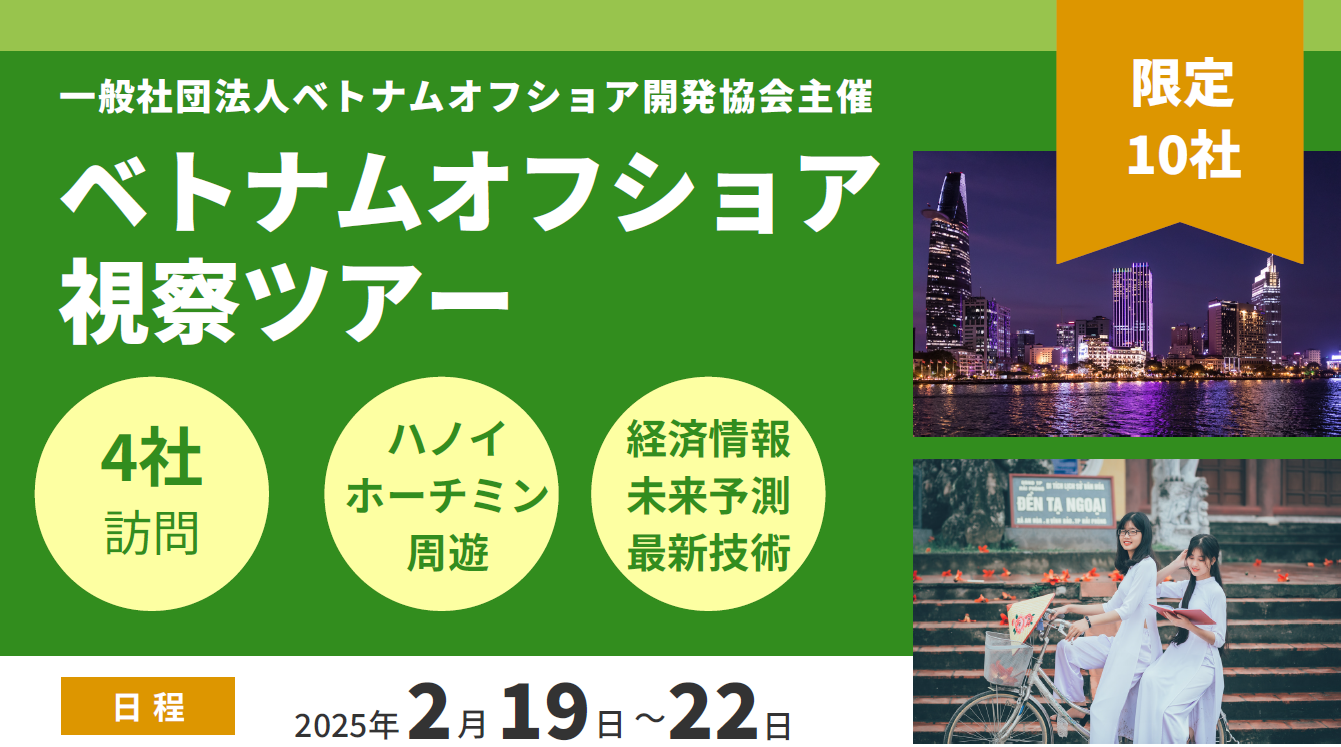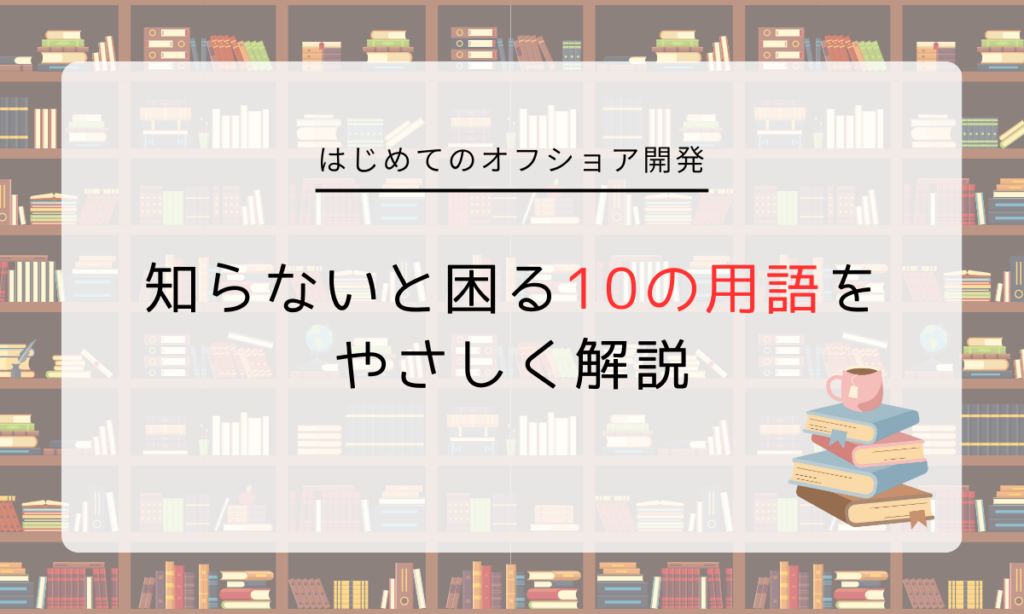
こんにちは!VOC事務局です。
オフショア開発を初めて経験する企業担当者にとって、最初にぶつかる壁は「専門用語」かもしれません。聞き慣れないカタカナ語、契約形式の違い、役割の名称──そのどれもが曖昧な理解のままプロジェクトをスタートさせると、誤解やミスに直結します。
たとえば「BrSEが対応します」と言われても、その役割を明確に理解していなければ、「何をどこまで任せていいのか」「自社側でどこまで説明すべきか」が分からず、気付けば想定外の成果物が上がってきた…という事態にもなりかねません。
オフショアでは文化も言葉も異なります。だからこそ「同じ言葉で同じことを指している」という前提をつくることが大事です。この記事では、はじめてのオフショア導入担当者が最低限知っておくべき10の基本用語を、背景や現場のあるあると一緒に解説します。
この記事はこんな人にオススメ!
1.なぜ“共通言語”が必要なのか?

オフショア開発では、言語が違うのはもちろん、文化も常識も仕事の進め方も異なります。日本ではあうんの呼吸や“空気を読む”コミュニケーションが成り立っていても、ベトナムではそれがまったく通じない、というのはごく自然なことです。
たとえば、日本では「PM」と言えば“全体を取り仕切るプロジェクト責任者”を指すことが多いですが、現地では“連絡係”くらいに解釈されていることもあります。逆に「QC」という言葉は、日本では「納品前のチェック係」くらいの意味でとらえられがちですが、ベトナムでは開発工程全体に関与するテスト設計者という意味で使われています。
つまり、同じ言葉でも前提がまったく違うことがあるのです。
だからこそ、用語の理解は“知識”ではなく、“コミュニケーション基盤”です。ここから、現場で必ず出てくる10のキーワードを1つずつ丁寧に解説していきます。
2.オフショア用語10選
① オフショア開発
まずは基本の基本。オフショア開発とは、海外の企業やチームに開発業務を委託することを指します。対象国としては、ベトナム・インド・フィリピンなどが多く選ばれており、その背景にはコスト・人材・スピードといったメリットがあります。
ただし、“安さ”だけで選ぶと危険です。技術力、コミュニケーション、体制など、価格以外の要素こそが成功/失敗を分けます。オフショアは単なる「外注」ではなく、パートナーとの協働であるという前提が重要です。
▼こちらの記事でオフショア開発の意味やメリットを分かりやすく解説しています▼
【簡単解説】オフショア開発とは?意味やメリットを5分で分かりやすくご紹介!
② ラボ型契約
ラボ型とは、月単位でエンジニアの稼働枠を確保し、柔軟にタスクを指示できる契約形態です。大きなメリットは、仕様変更に対応しやすいこと。特にアジャイル開発や長期のシステム保守で有効です。
しかしその一方で、仕様が曖昧なまま走り出してしまい、“なんとなく開発が進むが完成が見えない”状態になることも。成果物管理の意識が薄れると、クオリティもスケジュールも曖昧になります。
ラボ型を成功させるためには、定例ミーティングで進捗を可視化し、目的と優先順位を常に共有する体制づくりが不可欠です。
③ 請負型契約
請負型は、仕様と納期をあらかじめ確定し、それに応じた成果物を納品する契約形態です。メリットは、スコープと価格が明確な点。しかし仕様が決まりきっていない段階でこの形式を採用すると、途中変更が難しくなり、追加コストや納期遅延が発生するリスクもあります。
また、発注側が「請負なら全部やってくれる」と考えてしまうのも失敗のもと。要件定義の粒度が粗すぎると、受け手は仕様を補完できず、想定と異なるものが上がってきます。
請負型では、“完璧な設計書”が最大の成功要因と言っても過言ではありません。
▼こちらの記事で開発契約の種類について詳しく解説しています▼
【外注初心者必見】開発契約の種類と選び方をわかりやすく紹介
④ BrSE(ブリッジSE)
BrSEとは、日本側と現地側の橋渡しをするエンジニアのこと。日本語ができて、技術的な理解もあり、さらに文化的なニュアンスまで読み取ってくれる——そんな万能キャラとして期待されがちですが、当然個人差があります。
誤解されやすいのは、「BrSEがいるから全部伝わる」と安心してしまうこと。実際には、発注側が細かく背景を説明しなければ、BrSEも正確に翻訳できません。また、BrSEに頼りすぎると属人化しやすく、本人が抜けた途端にプロジェクトが崩れるというリスクも。
BrSEは頼る存在ではなく、一緒に翻訳・調整していくパートナーとして位置づけるのが理想です。
▼こちらの記事でBrSE(ブリッジSE)の仕事内容について詳しく解説しています▼
オフショア開発のブリッジSE(BrSE)の仕事内容をご紹介
⑤ QC(品質管理)
QCは、ソフトウェアの品質を担保する専門職です。バグを見つけるだけでなく、テストケースを設計し、リリース前に抜け漏れがないかを確認する役割も担います。
日本では開発者がテストも兼任するケースが多いですが、ベトナムではQCが独立して機能しているケースが一般的です。QCの成熟度によっては、「開発が終わった=すぐ納品」ではなく、「QCで1週間かかる」という前提を持つ必要があります。
プロジェクトの後半フェーズで納期がタイトになると、QC工程が削られることもありますが、それは品質低下を招く典型パターンです。
⑥ PM(プロジェクトマネージャー)
PMと聞くと、日本では「全部を統括してくれる責任者」というイメージを持つ方が多いかもしれません。ですが、ベトナム側のPMは“調整役”に近い立場で、要件定義や仕様策定は別のSEやBrSEが担当していることもあります。
この違いに気づかず、「PMに任せておけば安心」と思っていたら、誰も仕様の細部まで見ていなかった…という事態も珍しくありません。契約書やプロジェクト開始時のミーティングでは、PMの担当範囲を明文化することが欠かせません。
⑦ エスカレーション
エスカレーションとは、トラブルや判断が難しい案件が発生した際、速やかに上位層へ報告・相談することです。日本では「小さな火種のうちに相談する」文化がありますが、ベトナムでは「黙って対処してみる」「問題と気づかない」ケースも少なくありません。
特に若手エンジニアがトラブルを抱えたまま期限を迎え、「進捗が順調です」と報告しながら実は全然動いていなかった、というケースもあります。
このギャップを防ぐためには、「こういうときは必ず報告」「進捗が止まったらすぐ相談」といったルールを明確にし、報告しやすい雰囲気と評価制度を設ける必要があります。
⑧ 要件定義
オフショア開発では、要件定義書が命です。日本語で曖昧なまま進めてしまうと、伝わらないどころか誤解されてしまいます。
たとえば「ある程度柔軟に対応できる構成で」とか「違和感がないように」など、感覚的な表現はそのまま翻訳されても意味が通じません。数字・画面遷移・業務フローなど、視覚的に確認できる情報を添えることがとても重要です。
また、現地メンバーとの打ち合わせの中で不明点があれば、確認を受け身にせず、こちらからも定義の粒度を調整していく姿勢が求められます。
⑨ 通訳付き開発
初期段階でコストを抑える目的で、BrSEではなく「通訳者」を介してやり取りするケースもあります。もちろん、IT用語に精通した通訳者がいれば成立しますが、たいていはそうではなく、単に言語を訳すだけのケースが多いです。
結果として、技術的な背景や文脈が伝わらず、誤解が生じやすくなります。最悪なのは「通訳が訳してくれたから伝わったはず」と思い込んでしまうこと。双方に齟齬があっても、そのまま進行してしまうのです。
この形式は長期プロジェクトには向いておらず、将来的にはBrSE配置や社内に日本語スピーカーを育成する方向にシフトすべきでしょう。
⑩ 文化ギャップ
最後に、言語以上にやっかいなのが文化的なズレです。
- 日本:「確認しました」→内容を把握した
- ベトナム:「確認しました」→読んだけど理解していないかも
- 日本:「納期は間に合わせます」→調整してでもやり切る
- ベトナム:「できます」→できるか分からないけど前向きに言っておく
このように、“同じ言葉”でも背景にある価値観が異なるため、ミスコミュニケーションが起きやすいのです。
「曖昧な表現を避ける」「確認は文書で行う」「Yesでも詳細確認する」など、文化ギャップを埋める工夫をすることで、誤解と衝突を防ぐことができます。
▼こちらの記事でオフショア開発を行う上での5つのリスクについて詳しく解説しています▼
オフショア開発に潜む5つのリスク 失敗しないコツを押さえよう!
3.実践Tips:用語をチームで“共通言語”にするには?
用語を正しく理解していても、それがチーム内で共有されていなければ意味がありません。特にオフショア開発では、「現地メンバーはわかっていると思っていた」「別の拠点では違う意味で使われていた」といった齟齬が起きがちです。
そこで有効なのが以下のような取り組みです。
- 用語定義シートの配布
プロジェクト開始時に、使う予定の用語とその定義を整理して共有する。 - 会議ログに用語解釈を記録
定例MTGなどで用語のニュアンスが話題になったら、その解釈をログに残す。 - Wiki/Notion等でグロッサリー化
“用語集”として共有ドキュメントにまとめ、都度アップデートできるようにする。 - BrSEに頼りすぎず、発注側でもチェック
BrSEは強力な翻訳者ではあるが、100%依存すると属人化リスクが高まる。
おわりに:用語のズレは、品質のズレになる
この記事で紹介した10の用語は、すべて現場で頻繁に登場する基本中の基本です。
しかし、その意味や使われ方はチームや国によって微妙に異なり、放置すればプロジェクト全体に影響を及ぼします。
「言葉なんてわかるでしょ」ではなく、
「“このチームで”こう定義して使っている」という共通認識の醸成が、成功の土台になります。
そして、これはベテラン向けの話ではなく、むしろ初めてオフショアを担当する方こそ最初に知っておくべきことです。
メール配信申込みのご案内
ベトナムオフショア開発協会では、
日越の協業を進めるうえで役立つ考え方や、現場に基づいた知見を日々発信しています。
本記事の内容も含め、より詳しい情報は会員限定コンテンツとしてお届けしています。
セミナーや視察ツアーのご案内とあわせて、メールにてご案内しています。